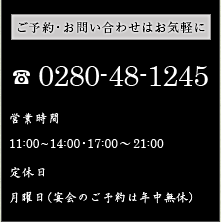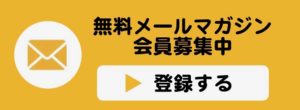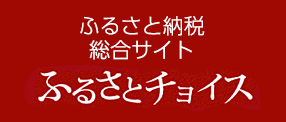みなさん、こんにちは!
今回はうなぎ業界の裏側に潜入してきた内容です。
「うなぎの養殖」と聞くと、なんとなく天然物より劣るイメージを持っていませんか?
実は、そんな先入観を覆すような驚きの現場がたくさんあるんです!
浜名湖をはじめ、全国各地の養殖場を訪問して分かった衝撃の事実。
安全管理の徹底ぶりや、魚たちへの愛情たっぷりの育て方、
そして何より生産者さんたちの熱い想いに触れて、養殖に対する見方が変わってしまいます(^^)
「魚にストレスを与えない環境づくり」「徹底した水質管理」「エサへのこだわり」など、
消費者には見えない部分での努力が、実は私たちの食卓の安全と美味しさを支えているんですね。
この記事では、各地の養殖のプロフェッショナルたちとの対話を通して見えてきた、
うなぎ業界の知られざる舞台裏と情熱をお届けします。
うなぎの見方が変わる、そんな発見の旅にぜひご一緒ください!
1. 【驚愕】養殖場の裏側に潜入!
知られざる安全管理の実態とは

養殖うなぎは「自然のものより劣る」というイメージをお持ちではありませんか?
実は最新の養殖技術と徹底した安全管理によって、その認識は大きく変わりつつあります。
今回、普段は立ち入ることのできない養殖場の内部に潜入取材し、
驚くべき実態が明らかになりました。
静岡県の浜松でのうなぎ養殖場では、24時間体制の水質モニタリングシステムを導入しています。
水温、酸素濃度、塩分濃度などの数値がわずかに基準値を外れると、
担当者のスマートフォンにアラートが送信される仕組みです。
「夜中に警報が鳴って急いで対応することも珍しくありません」と語るのは、
現場責任者の古橋さん。
生産者たちの寝食を忘れた管理体制が、安全な養殖魚を支えています。
また、最近のうなぎ養殖では革新的な手法を取り入れています。
「餌の成分を研究開発しての養殖」を実現し、
これまでオス化にかたよっていたうなぎの生態をメス化にできる特殊な餌の開発に成功。
通年の品質にはどうしてもばらつきが生じやすいのがうなぎなのですが、
こうした取り組みによって一年中身の質が安定したうなぎを育てることが可能になりました。
というお話です。
生態の謎が多いうなぎの健康状態を定期的に検査し、
データに基づいた科学的な養殖管理を行っています。
さらに注目すべきは、静岡県焼津でのこれまた特殊なうなぎ養殖。
伏流水をふんだんに使用し、擬似的に四季を体験させての育成をすることで、
天然に最も近い状態のうなぎの育成をすることに成功しています。
「育成期間は約2倍かかりますが、品質を最優先に考えた結果です」と語る生産者の言葉に、
その覚悟が感じられます。
養殖場での安全管理は想像以上に厳格で科学的。
「自然のものより安全性が高い場合も多い」というのが専門家の見解です。
2. うなぎが教えてくれた本当の話 - プロたちの苦労と想い
うなぎ養殖の品質は、生産者の情熱と日々の管理にかかっています。
「うなぎは正直で、ちょっとでも水質が悪くなれば、すぐに反応する」と語るのは
生産者だけでなく、流通の橋渡しをする問屋さんでも同様。
特に水質管理には細心の注意を払っており、
養殖場の水質なども加味して出荷時に均一になるように
日々の管理をしています。
早朝暗いうちから始まる作業では、定期的な水質検査、うなぎの健康状態のチェックなど。
休む間もなく続く作業の中で、微妙な変化は匂いでわかるそうです。
「動き方、色つや、身の張りや輝き。これは経験でしか分からない」とのことで、
最新技術と職人の勘が融合することで、高品質なうなぎが安定的に届けられています。
「消費者には知ってほしい。養殖は自然との共存です」と現場の方はおっしゃいます。
天災、魚病、価格変動—養殖業は常にリスクと隣り合わせで、
特に知られていないのは、うなぎの稚魚は天然資源であることです。
このおおもとの稚魚が不足してしまうと
養殖して育てることすらままならないのです。
うなぎの研究をしている大学の先生からは、
もっと気にしてほしいのは自然環境であって、おおきな自然のサイクルを取り戻すことが
一番の近道ともおっしゃっておりました。
ただ、そんな事実も知らされないまま
まったく稚魚が不漁という年もありました。
その時はうなぎ価格は異常なくらい高騰し、マスコミもこぞって煽り報道をしたせいか
その年のうなぎの品質をはじめ需要のあんばいも雰囲気が悪く、
価格にそった内容かどうかという点も含めて全体的に良い影響をもたらしませんでした。
悲しいかな、
消費者の関心が表面的だったところがとても悔やまれます。
養殖業〜流通業者さんたちの苦労は、
消費者の食卓に届くことはほとんどありませんが、
プロたちは口を揃えて安全な食べ物を届けることが
あたり前とされてます。
そこに至るまでの日々の細やかな苦労の大切さは
現場を知っている人たちだけが知りうるものです。
全国の現場で出会った生産者〜お店の方たちは、単なる「うなぎを売る人」ではなく
未来の食を支える情熱にあふれており、地域の方と開発したり、
新しい販路や体験を通じて食文化をつないでいっています。
各地で率先して挑戦している方々と交流すると、
いつもその先を見据えていて話が尽きないところが楽しいですね(^^)
3. 「うなぎの住みやすさ」にこだわる養殖場の秘密 –
現場から見えた真実

うなぎ養殖の品質を決める最大の要素は「住環境」だと言われています。
実際に現場を訪ねると、その言葉の重みがはっきりと理解できました。
ストレスなく泳げる空間を確保しています。
「密飼いすると病気のリスクが高まり、薬に頼る養殖になってしまう」ということから
とにかく環境を良い状態に保つため、
目に見えない細かいところをチェックできるようになっています。
驚いたのは水質管理の徹底ぶりです。
多くの養殖場では1日1回の水質チェックが一般的ですが、
先進的な養殖場では最新のIoTセンサーを導入し、
酸素濃度やpH値を24時間モニタリング。
異常値を検知すると担当者のスマートフォンに即座に通知が届く仕組みを構築しています。
養殖業界では「良い環境で育てれば薬に頼る必要がない」という考え方が広がりつつあります。
最先端の設備投資と昔ながらの魚を観察する目が融合した現場には、
日本の養殖業の未来を感じました。
消費者が知らない養殖現場の秘密は、
実は「自然に近づける」という、とてもシンプルな哲学にあったのです。
4. 地元で愛される理由 - 全国巡ってみて

全国各地のうなぎの名産地を巡ると、ある共通点として「地元愛」の強さというか
地域との親密度がたかいことが気になりました。
「地元の人に喜んでもらいたい」というかいっしょに育っていこうという想いが強い感じ。
こんなにも全国を歩き回ることの始めは
何気ない親の一言からでした。
所属していた団体の活動を話ししていたところ、
「そんなにまちづくり」っていうなら
うなぎでまちづくりしたらいいんじゃない?
で、はじめて調べて行き着いたのが「うなぎのまち岡谷」の事例。
ここでは冬に土用の丑の日を称したうなぎまつりを実施していたことがあって
最初は「冬にうなぎ売れたらいいな」という
いたって不純な動機からスタートしたのでした。
最初はわけもわからず岡谷市に直接話しを聞きに行って
窓口を突撃訪問。
事前のアポ無しなのに色々と紹介をしてくださり、
なんとも無謀すぎる始まりでした。
そこからは地元の商工会議所の支援を受けて
岡谷市との交流が始まりました。
まつりを始めるには何から準備したらいいのか
また、どういう後援や協力が必要なのか?
集客はどうすればいいのか?
販売はどうすればいいのか?
さっぱりわからないことを丁寧に教えていただき
次の支援候補地を紹介いただきました。
それが「浦和のうなぎを育てる会」。
ここでは大森さんをはじめ沢山の方に支えられ、
その規模感の大きさや来場者数の多さもあって
今でも5月のうなぎまつりには参戦してお手伝いをさせてもらってます。
ここでは詳細は省きますが、
各地のうなぎや川魚料理提供する地域をとにかく巡り巡って
その環が全国的に広がっていくのを毎年感じながら
楽しく活動を続けております。
5. 生産地と価格の意外な実態。

うなぎの養殖の卸価格というのは、
実は全国的に一律の相場が決まっていてあまり価格帯の差がありません。
その年の稚魚の状況や社会情勢で決まっているそうです。
意外なのが月によっては、
その価格が輸入品と逆転することもあり、
国産よりも中国産のうなぎのほうが高いときもあったりします。
このあたりはなにがなんだか未だよくわかりません。
さて、
国内のうなぎでもブランド鰻と呼ばれるものは例外の値で設定されてます。
ただ、そうはいってももともとの流通量が少ないこともあり、
おいそれと仕入れることができない鰻がほとんどです。
わたしも以前に調べて
マニアックな生産者さんに問い合わせてみたことがありますが、
生産者との密な信頼関係が得られるまでは出荷まで至らず。
「すでに決まっているところにしか卸せません」と、
きっぱり断られてしまったこともあります。
そんな高いうなぎの味の違いはというと、
よっぽど食べ歩いていて
よーく味わうとその深みや濃さがちがうのがわかるのですが、
個人的には価格の差でいうなれば
そこまでの違いがわかる方は少ないと思ってしまいます。
仕入れから調理まで一貫しての技術と知識が伴っていれば
ある一定のおいしさであるのがうなぎだと思っています。
なので、鰻に関していうなれば
ファーストフードやスーパー、コンビニで
扱っているものでもレベル高いものもあったりして
その研究する熱量には感心してしまうこともあります。
その価格でよくここまでとおもう
とはいえ
うなぎは最近高くて贅沢品になってしまいました。
お気軽に食べられる価格であってほしいと感じるのと、
お店的には手間を考えるともっと価格を上げてもいいのかなと
ジレンマに陥っています。