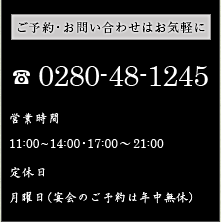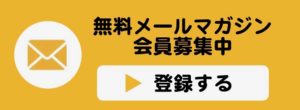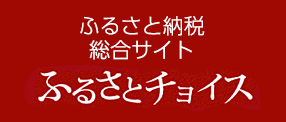「うなぎが高い!」と思ったことはありませんか?
スーパーで見かけるうなぎの価格に驚いた経験、誰にでもあるはずです。
特に土用の丑の日が近づくと、その価格はさらに跳ね上がりますよね。
実は、この高騰の背景には、
私たちが普段知ることのない養殖の苦労や複雑な流通の仕組みが隠されています。うなぎが赤ちゃんから食卓に並ぶまでには、想像を超える道のりがあるんです。
このブログでは、うなぎ養殖のプロフェッショナルの視点から、価格高騰の真相に迫ります。なぜうなぎはこんなに高いのか?どうすれば少しでもお得に購入できるのか?さらには、絶滅危惧種に指定されているうなぎを持続可能な形で消費していくにはどうすればいいのか?
知れば知るほど奥深いうなぎの世界。
この記事を読めば、次にうなぎを食べるときの見方が変わること間違いなしです!
うなぎ好きの方も、単純に「なぜこんなに高いの?」と疑問に思っている方も、
ぜひ最後までお付き合いください。
1. うなぎの値段がなぜこんなに高い?
知らなかった養殖の驚きの真実

土用の丑の日になるとスーパーやデパ地下で目にするうなぎの価格表示。
一尾5,000円、一枚3,000円と年々上昇する価格に
「なぜこんなに高いの?」と驚く方も多いのではないでしょうか。
実はうなぎが高額な理由には、知られざる養殖の苦労と複雑な流通システムが関係しています。
うなぎの養殖は「完全養殖」が極めて難しい水産業界の難題の一つです。
シラスウナギ(稚魚)は天然で捕獲されたものを育てる「養成」が主流であり、
この天然シラスウナギの漁獲量が激減しているのです。
日本国内では年間約20トンしか捕れず、中国や台湾からの輸入に頼っている状況です。
さらに驚くべきことに、養殖場でのうなぎの生存率はわずか70%程度。
水温や水質の管理が非常にデリケートで、一度でも条件が崩れると大量死することもあります。
宮崎県や静岡県など全国的に有名なうなぎ養殖場では、
24時間体制での監視と、特殊な餌の開発に年間数千万円の投資をしているといいます。
また、養殖から食卓までの流通経路も複雑です。
シラスウナギの仲買人、養殖業者、加工業者、卸売業者、小売店と、
実に5段階以上の業者を経由するため、その都度マージンが上乗せされていきます。
国際的な規制も価格を押し上げています。
ニホンウナギは2014年にIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストに
「絶滅危惧IB類」として掲載され、国際取引にも制限がかかるようになりました。
うなぎ一尾の価格が高い理由は、このように供給不足、
養殖の難しさ、複雑な流通システム、そして環境保全のための規制が重なった結果なのです。
値段だけでなく、一尾のうなぎにかかる労力と時間を知ると、
その価値がより理解できるのではないでしょうか。
2. プロが教える!高騰するうなぎを
少しでもお得に買う方法とタイミング
高級食材として知られるうなぎですが、近年の価格高騰により、
庶民の食卓からは遠い存在になりつつあります。
しかし、購入のタイミングや方法を工夫すれば、
比較的リーズナブルにうなぎを楽しむことが可能です。
お得にうなぎを購入するためのプロの知恵をご紹介します。
まず押さえておきたいのが「曜日」です。
流通の要を担う市場などでは、
通常水曜日、日曜日に休むことが多く、
その合間に仕入れたものを流通させなくてはなりません。
多くのスーパーでは火曜日から水曜日にかけて入荷が増え、
値下げの可能性が高まります。
特に水曜日の夕方は週末に向けた入れ替えの時期で、
前週からの在庫を処分する傾向があるため、
通常より1〜2割ほど安く購入できることがあります。
次に「季節外れ」を狙うことも効果的です。
土用の丑の日を避け、9月〜11月頃のオフシーズンを狙えば、
需要減少に伴い価格が2〜3割下がることも珍しくありません。
この時期は冷凍うなぎをストックしておくのがおすすめです。
購入場所も重要なポイントです。大型スーパーよりも、
築地市場や大阪の黒門市場など専門市場に隣接した専門店の方が、
中間マージンが少なく割安な場合があります。
また、イオンやコストコなどの大型店では、
PB商品として比較的リーズナブルなうなぎを提供していることがあるので要チェックです。
うなぎの「カット商品」も見逃せません。
一尾丸ごとではなく、半身や端材を使った「うなぎカット」は、
通常の蒲焼より3〜4割安く提供されていることがあります。
味は変わらないため、見た目にこだわらなければ経済的な選択肢となります。
インターネット通販も活用すべきでしょう。
「うなぎタイムセール」で検索すると、
楽天市場やAmazonなどで期間限定の割引販売を見つけることができます。
特に産地直送の通販サイトからの購入は、
中間マージンが削減され、直でうなぎを適正価格で入手できる可能性があります。
〇〇組合といった養殖場直営サイトがおすすめです。
最後に、「予約」という方法も見逃せません。
土用の丑の日の1ヶ月以上前に予約すると、
早割として1〜2割引きになるケースが多いです。
老舗うなぎ店の多くがこのシステムを採用しているので、
計画的な購入を心がけましょう。
これらの方法を組み合わせれば、高騰するうなぎ価格の中でも、
できるだけ賢く美味しいうなぎを楽しむことができるはずです。
価格だけでなく、産地や調理法にもこだわって、最高のうなぎ体験を目指しましょう。
3. うなぎ価格の裏側にある「流通の闇」
〜消費者が知らされていない現実

うなぎの値段が高騰している背景には、
消費者にはほとんど知られていない流通構造の問題があります。
うなぎが生産者から私たちの食卓に届くまでには、
実に5〜7段階もの中間業者が介在しているのです。
まず、シラスウナギ(稚魚)の採捕業者から養殖業者へ。
次に養殖業者から産地仲買人へ。
さらに産地仲買人から消費地卸売業者へ。
そして小売店やレストランへと渡っていきます。
この長い流通経路のそれぞれで利益が上乗せされ、
最終的な価格は当初の2〜3倍にまで膨れ上がります。
特に問題なのが「買い占め」の実態です。
シーズン初期に大手流通業者がシラスウナギを高値で買い占めることで、
中小養殖業者は仕入れ価格の高騰に苦しめられます。
大手水産商社の中には、養殖業者に対して
「うちから買わなければ今後シラスウナギは供給しない」という
圧力をかける事例も報告されています。
また、輸入うなぎの流通においては、
原産国の偽装問題も深刻です。
ワシントン条約で取引が制限されている種が、
別の種として流通していることもあります。
特に中国からの輸入品では、トレーサビリティ(生産履歴の追跡可能性)が
不十分なケースが少なくありません。
消費者が知らない現実として、スーパーマーケットでの
「特売うなぎ」の多くは、実は冷凍保存されていた前年以前の在庫だったり、
養殖環境や飼料に問題があるものが含まれていたりします。
「国産」と表示されていても、
実はシラスウナギは外国産というケースも珍しくありません。
こうした複雑な流通構造を改善するため、
直販システムを導入する養殖業者も増えています。
〇〇組合といったうなぎの養殖場での販売サイトでは
インターネット直販で中間マージンをカットし、
高品質なうなぎを比較的リーズナブルな価格で提供することに成功しています。
消費者としては、うなぎを購入する際には、
単に価格だけでなく、どこで養殖され、
どのような流通経路を経てきたのかという点も意識することが大切です。
透明性のある流通を選ぶことが、結果的に持続可能なうなぎ産業を支えることにつながります。
4. 激変するうなぎ市場!
絶滅危惧種から考える持続可能な消費とは

ニホンウナギが国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで
「絶滅危惧種」に指定されたことをご存知でしょうか。
この指定は、私たちの食文化に大きな警鐘を鳴らしています。
うなぎ市場は今、大きな転換点を迎えているのです。
かつては庶民の味だったうなぎが、
今や高級品となった背景には単なる資源減少だけでなく、
国際的な需要と供給のバランス崩壊があります。
中国や韓国、台湾などアジア各国でもウナギの消費が増加し、
シラスウナギ(稚魚)の争奪戦が激化しています。
国際的な保全への取り組みとして、
東アジア各国による「ウナギの資源管理に関する国際協力体制」が構築され、
シラスウナギの漁獲量制限が導入されました。
これにより、違法取引の阻止や資源保護が図られていますが、
市場価格の上昇は避けられない状況です。
持続可能なうなぎ消費のために私たちができることは何でしょうか。
まず「完全養殖」技術の発展に注目すべきです。
天然シラスウナギに依存しない養殖サイクルの確立は、
資源保護の鍵となります。
現在、国立研究開発法人水産研究・教育機構などが研究を進めており、
商業化への道のりは険しいものの、着実に進展しています。
また消費者としては、ASC(水産養殖管理協議会)などの
持続可能な養殖を認証する制度を参考に商品を選ぶことも重要です。
認証を受けた養殖場のうなぎは、環境負荷が少なく、適切な管理のもとで育てられています。
土用の丑の日だけでなく、
うなぎを一年中消費する文化も見直すべき時期に来ています。
特定の日に集中する需要が価格高騰と資源枯渇を加速させるからです。
うなぎを「特別な日の特別な食べ物」として、
その価値を再認識することも持続可能な消費につながります。
うなぎ市場の激変は、私たちの食文化と環境保全のバランスを問う重要な課題です。
高価格化はマイナス面だけでなく、資源の価値を再評価する機会とも捉えられます。
次世代もうなぎを楽しめる社会を目指し、消費者、生産者、
行政が一体となった取り組みが求められています。
5. うなぎ養殖のプロが明かす!
本当においしいうなぎの見分け方と調理法

うなぎを選ぶとき、多くの人が「どれを選べば失敗しないのか」と悩みますよね。
実は、うなぎ養殖に3携わるプロの目線では、
品質の良いうなぎには明確な特徴があるのです。
なかなか活きたうなぎを取り扱うことは家庭ではありませんので、
これは仕入れる側のプロ目線です(^^)
まず、良質なうなぎの見分け方は「ツヤ」にあります。
健康に育ったうなぎは皮に自然な光沢があり、黒みが強く均一な色をしています。
また、腹部は白っぽく、その境界線がくっきりしているものが理想的です。
次に注目すべきは「太さと硬さ」です。
均一な太さで、触ったときに適度な弾力を感じるものが活きの良さの証。
腹のあたりがブヨブヨだとあまり育ちが良くないです。
このしまり具合からいざ、さばいていくときにまた見分けがあります。
まず、頭の付近に切込みを入れてうなぎをおとなしくさせます。
その後目打ちであたまを固定し、先程の切込みから
骨に沿って包丁を進めていきます。
このときの骨にあたった感触が柔らかいのがいいうなぎ、
また硬くて包丁が進まないのはヒネといって、固いうなぎの可能性が高いです。
そうしてさばいていくときに身の脂ののりもわかります。
夏に向けて育ったうなぎはけっこうさっぱりとしていて、
秋冬のうなぎは脂がのってしっとりとした感じです。
これはさばいたときにもう手の感触でわかるほど違うものです。
個人的には秋冬のうなぎをもっと食べてほしいところですね(^^)
最後に、プロが教える意外な事実として、
うなぎは必ずしも「超高級品」を選ぶ必要はないということ。
中価格帯でも適切な養殖環境で育ったうなぎは十分に美味しく、
むしろ日本の養殖技術は世界最高水準であるため、国産であれば一定以上の品質は保証されています。
養殖場の水質管理や餌の品質にこだわっているブランドうなぎを選べば、失敗はほとんどありません。ネットで調べると色々出てきますが、おおむねブランド名がついているものは
プロの間でも高い評価を得ています。
これらのポイントを押さえれば、家庭でも専門店に負けない
美味しいうなぎを楽しむことができるでしょう。
(家庭でさばいて焼くのは至難の業ですが(笑))
値段だけでなく、これらの見分け方を知っておくことが、本当のうなぎ通への第一歩です。