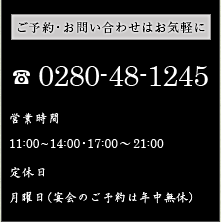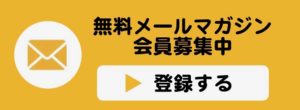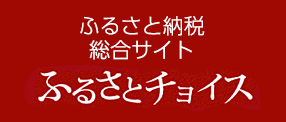こんにちは。「うなぎ昇り小松園」の小倉です。
「丑の日って、なんでうなぎなの?」
…お客様からもよくいただくこの質問。
暑〜い夏に、なぜかうなぎを食べるこの習慣。
でも実は、その由来をきちんと知っている方は意外と少ないのです。
今日は、土用の丑の日のちょっと不思議で、ちょっと面白い“うなぎと日本人の深い関係”についてご紹介します。
【1. 土用の丑の日って、そもそも何?】
「土用」とは、実は“夏”を表す言葉ではありません。
暦の上で、春夏秋冬それぞれの季節が移り変わる直前の約18日間のことを「土用」と呼びます。
なかでも「夏の土用」は、1年で最も暑さが厳しい時期として知られています。
そして「丑の日」とは、十二支(子・丑・寅…)の中の「丑」にあたる日。
つまり「土用の丑の日」とは、“夏の土用期間に訪れる丑の日”という意味なのです。
【2. なぜ「う」のつくものを食べる? うなぎの始まり】
ここからが面白いところ。
江戸時代、夏場にうなぎが売れずに困っていたうなぎ屋さん。
そこで登場したのが、あの有名な学者「平賀源内」です。
「“丑の日には『う』のつく食べ物を食べると夏負けしない”って、張り紙してみたらどう?」
この機転が当たり、みるみるうちにうなぎが売れたとか。
以来、夏の丑の日に「うなぎを食べる」風習が広がったというわけです。
【3. でも実は、もっと深い理由もあるんです】
確かに、平賀源内の話は“うなぎ販促の成功例”として有名ですが、
実はそれだけではありません。
うなぎには、栄養素がたっぷり。
ビタミンA、B群、D、E、そして良質なたんぱく質。
特に夏の暑さで失われがちな栄養をしっかり補ってくれる、まさに“夏の養生食”なのです。
古来より日本では、「食べ物には力が宿る」とされてきました。
うなぎもその一つ。
季節の変わり目に“精のつくもの”をいただいて、夏を乗り切る。
そういう「暮らしの知恵」が、今も私たちの食卓に残っているんですね。
【4. うなぎを食べることの「意味」を、いま一度見つめてみる】
私たちが、土用の丑の日にうなぎを用意する理由。
それは、単に「イベントだから」ではありません。
「大切な人に、元気でいてほしい」
「暑さでバテないように、食べやすくて栄養のあるものを」
そんな思いやりが、うなぎという食べ物に込められてきたのだと思うのです。
【まとめ:想いを込めて、今年も丑の日にうなぎを】
昔の人たちが守ってきた「季節の習慣」には、ちゃんと意味があります。
土用の丑の日にうなぎをいただく――
それは、「家族の健康を願う」、そんな小さな祈りの形かもしれません。
今年の丑の日も、ぜひ一口召し上がってみてください。
香ばしい香りと、ふわっとした食感。
そして何より、“食べることで、元気になる”体験を。
「うなぎ昇り小松園」では、そんな気持ちを込めて、
一尾一尾、大切に焼き上げています。
\ ふっくら香ばしいうなぎをお探しの方へ /
▶︎「十一代目うなぎ佐市右衛門」のオンラインストアをのぞいてみる