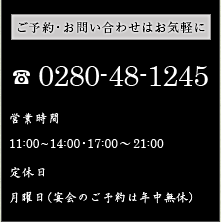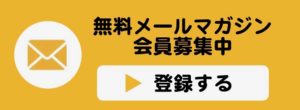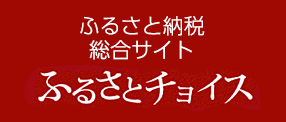皆さん、こんにちは!茨城県古河でうなぎ専門店
「うなぎ昇り小松園」、通販サイト「十一代目うなぎ佐市右衛門」をやっている小倉です。
いつもスーパーとかでうなぎを見たとき、「あ、美味しそう!」って思いますよね。
でも、実はうなぎって、私たちが普段知っている以上に、
すっごく長い「歴史」を持っている生き物なんです。
そして、何を隠そう、私自身もこの「うなぎの歴史」と、
お店の歴史、そして自分の家族の歴史の中で、ずーっと生きてきた人間なんです。
今回は、そんなうなぎの、そして私の、知られざる「歴史」のお話しを、
ちょっとだけお話しさせてください。
これを読んだら、いつものうなぎの見方が、もしかしたら変わるかもしれませんよ。
【へぇ~!】知ってた?うなぎって、とんでもなく昔から食べられてるんです

うなぎが日本の歴史にどれくらい前から出てくるかって言うと、
これがもう、びっくりするくらい昔なんです。
縄文時代の遺跡からうなぎの骨が出てきたり、
なんと奈良時代の『万葉集』っていう昔の歌集にも、うなぎの歌が載ってたりするんですよ。
これって、
「あ、昔から日本人はうなぎが好きだったんだな~」ってことですよね。
江戸時代になると、今でもみんなが知ってる「土用の丑の日」に
うなぎを食べるっていうのが流行りました。
これは、「夏、うなぎが売れないな~困ったな~」って
思ってたうなぎ屋さんか誰かが、
平賀源内っていう有名な人に相談したら、
「じゃあ『本日丑の日』って貼り紙出してみたら?」って言われてやってみたら、
これが大ヒットした!っていう説があるんです。面白いですよね、
昔からうなぎを売る人も一生懸命だったんだなぁって(笑)。
時代が進むにつれて、うなぎって、最初はきっともっと身近な感じだったのが、
だんだん「ちょっと特別な日」とか「元気を出したい時」のご馳走になっていったみたいです。
こういう歴史を知ると、うなぎがまた違って見えてきませんか?
【我が家の場合】江戸末期から「おもてなし」?私の名前にも歴史があるんです

さて、ここからはちょっと個人的な歴史のお話しになります。
うなぎの歴史は、実は私の家族の歴史とも繋がってるんです。
うちの小倉家っていうのは、ずーっと昔、江戸時代の文政の頃に、
初代の「佐市右衛門」が、
この古河の地でちょっと偉いさん(庄屋さん)みたいなことをやってたみたいなんです。
で、お客さんが来たり、なんか季節の行事があったりする時には、
心を込めた「おもてなし」料理を振る舞ってたって伝えられてるんです。
私の通販サイトの名前、「十一代目うなぎ佐市右衛門」っていうのには、
この江戸時代から続く「おもてなし」の気持ちと、
歴史を大事にしたいっていう思いが込められてるんですよ。
そして、そんな歴史を受け継ぐうちの父が、
ここ古河で「小松園」っていうお店を開けたのが、
昭和44年12月、父がまだ29歳っていう、
今考えると「若っ!」ってくらいの時でした。
慣れない場所でゼロから始めるのは、
それはそれは大変だっただろうなぁって思います。
名字は小倉なのになぜか「小松園」というのは、
実は父のお兄さん、つまり私の伯父さんが付けてくれたんです。
当時、伯父さんは不動産屋さんをやってて、
父がお店を開けるのをすっごく応援してくれたみたいなんです。
お店の庭に小さな松を植えて、「この松が大きくなるみたいに、
お店もどんどん大きくなって繁盛しますように」っていう願いを込めて、
名前を考えてくれたそうです。
父はきっと、これから頑張るぞ!って希望でいっぱいだったと思うんです。
でも、開業してほんの3ヶ月後、
伯父さんが事故で突然亡くなってしまったんです。
自分の不動産事務所を開く直前だったって聞いてます。
いつも明るくて元気だった父が、一人、
実家の蔵の中で泣いてたっていう話しを後から聞きました。
今、父はもうお店からは引退してますけど、
あの頃の事故のことを詳しく聞いたことはないんです。
話そうとしないっていうか、ただ遠い昔を思い出すような顔をするだけで…。
大人になって、その父の姿を見るたびに、
「あぁ、あの時、どれだけ辛かったんだろうか…」って思います。
それ以上は今でも聞けないですね。
小松園の始まりには、こんな風に、名前をつけてくれた伯父さんの思いと、
父の深い悲しみが刻まれてるんです。
【私の歴史】料理屋と料理屋の間で育ち、「想い」を学んだ子供時代

私が昭和48年11月26日に、この茨城県で生まれてからは、
もう生活の全てがお店のすぐそばでした。
文字通り、お店と家が一緒だったんです。
料理屋の息子として育った私の子供時代は、周りの友達とはちょっと違ったかもしれません。
「週末は遊ぶぞー!」じゃなくて、「週末は働くもの」みたいな(笑)。
両親は夜遅くまで、それはもう一生懸命働いてました。
私が幼稚園に通う頃には、もうよくお店の手伝いをさせられてましたね。
お客様のお皿洗いをしながら、パートさんが作ってくれる夜ご飯を食べるのが、
私にとっては当たり前の日常でした。
でも、うちって父の方も料理屋ですけど、
母の実家も群馬県の館林で、結構大きなお料理屋さんをやってたんです。
だから、週末になると、父方と母方、お互いの親戚同士が店を行ったり来たりして、
いとこたちとそこで遊んで過ごすっていう、
今考えるとなかなか面白い家族だったんですよね。
子供ながらに、暇そうにしてると見つけられては、
あれこれとお店の用事を頼まれて働かされるっていう(笑)。
親族みんながそんな感じで、「えぐいなぁ」って思ったこともありましたよ。
【歴史の継承】コロナ禍、そして全国へ ~「おもてなし」のバトンを次の時代へ~
日本のうなぎの歴史、私の家系の歴史、お店の歴史、そして私自身の幼少期の歴史。
こんな風に、私はずーっとうなぎと、そして料理というものに関わって生きてきました。
そんな中で、
つい最近、私たちのお店も歴史に刻まれる大きな出来事を経験しました。
皆さんご存知の通り、コロナ禍です。
今まで会食や宴会が中心だったお店には、お客様がほとんど来なくなってしまいました。
お店と、そこで一緒に頑張ってくれてるスタッフ、
そして取引先の方たちを守るために、どうすればいいか必死で考えました。
そして、父がゼロからお店を開業した時の大変さを思いながら、
「今こそ、動く時だ。この味と、おもてなしの心を絶やしちゃいけない」と決意したんです。
そうして始めたのが、通販サイト「十一代目うなぎ佐市右衛門」です。
通販なんて全く経験がなかったので、正直、不安だらけでした。
でも、ありがたいことに、食材ロス支援のサイトに載せてもらったり、
クラウドファンディングで応援してもらったり、銀行さんが取引先を紹介してくれたり…。
本当にたくさんのご縁と、お客様からの嬉しい声に助けられて、
少しずつですが、全国の皆さんに私たちのうなぎを届けられるようになりました。
通販っていう、父たちの時代には考えられなかった形ですけど、
やっていることは同じなんです。
江戸時代から続く家系の「おもてなし」の心、
父が苦労して築いたお店の味、そして私が子供の頃から学んだ料理への「想い」。
これら全部を、パックの一尾一尾に込めて、全国のお客様に届けたい。
そして、この素晴らしい日本のうなぎ文化を、
次の時代へしっかりと繋いでいくこと。それが、今の私の使命だと思っています。
まとめ:
どうでしたか? うなぎって、ただ美味しいだけじゃなくて、
こんなに深くて、たくさんの人の想いや歴史が詰まってるんです。
日本の歴史をたどっても、私の家族の歴史を見ても、
そして私自身の小さな歴史を見ても、うなぎはいつもそばにいてくれました。
これからも、うなぎが持つ遥かな歴史に敬意を払いながら、
そしてお客様への「おもてなし」と「想い」を一番大切にして、
最高のうなぎを焼き続けていきます。「十一代目うなぎ佐市右衛門」として、
この味と心意気を、もっともっとたくさんの方にお届けできたら嬉しいです。
ぜひ皆さんも、次にうなぎを食べる時には、
今日お話ししたちょっとした「歴史」に、ほんの少しだけ思いを馳せてみてくださいね。
きっと、いつもの一杯が、もっともっと美味しく感じられるはずですよ!