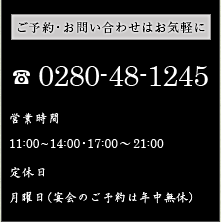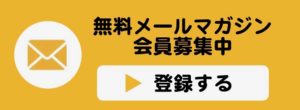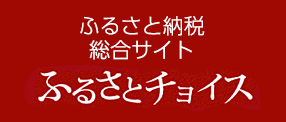こんにちは!夏になると無性に食べたくなるうなぎ。
でも最近、「うなぎが絶滅危惧種になっている」
というニュースを耳にしませんか?
特に国産うなぎの減少は深刻な問題となっています。
老舗の味や伝統はお金に代えがたいものがありますね。
でも「国産うなぎ」と言っても、
実はいろんな裏側があるんです。
どうやって見分けるの?なぜこんなに減っているの?
私たちにできることは何?そんな疑問にお答えします。
今回は、うなぎ好きな方はもちろん、
日本の食文化や環境問題に関心のある方にも読んでいただきたい内容になっています。
土用の丑の日だけでなく、一年中楽しめるうなぎの魅力と、
その未来を守るためのヒントをご紹介します!
さあ、国産うなぎの深い世界へ一緒に飛び込んでみましょう!
1. うなぎ危機!国産うなぎが消える前に知っておくべき真実

ニホンウナギが絶滅危惧種に指定されていることをご存知でしょうか。
かつては夏の風物詩として当たり前に食卓に並んでいた
「うな重」や「蒲焼」ですが、今や国産うなぎは危機的状況に陥っています。
国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでは
「絶滅危惧IB類」に分類され、
このままでは日本の食文化から姿を消してしまう可能性があるのです。
国産うなぎの漁獲量は最盛期の1/100以下にまで減少しました。
その原因は複合的で、河川環境の悪化、生息地の消失、乱獲などが重なっています。
特に深刻なのが、シラスウナギ(稚魚)の極端な減少です。
天然のシラスウナギが減れば養殖用の稚魚も確保できず、
結果として市場に出回るうなぎの価格高騰と品薄状態を引き起こしています。
実はスーパーやうなぎ専門店で販売されている「うなぎ」の多くは輸入物で、
中国や台湾などから輸入されたものが大半を占めています。
しかし、これらの多くも日本のシラスウナギを持ち出して海外で育てられたものであり、
根本的な解決にはなっていません。
業界団体「日本養鰻漁業協同組合連合会」の取り組みでは、
資源保護のための漁獲制限やトレーサビリティの強化などが進められていますが、
消費者である私たちにもできることがあります。
例えば、「浜名湖うなぎ漁協」などでは持続可能な活動として
毎年うなぎの放流などを行っております。
国産うなぎを守るためには、その危機的状況を正しく理解し、
適切な消費行動を選ぶことが重要です。
次回の土用の丑の日には、うなぎを「いただく」という感謝の気持ちとともに、
その希少性と価値を再認識してみてはいかがでしょうか。
2. 知らないと損する!
国産うなぎの見分け方と美味しさの秘密
国産うなぎと外国産うなぎ、
スーパーの棚に並んでいると見分けるのが難しいと感じたことはありませんか?
実は、見分け方を知っているだけで、
あなたの食卓に本物の国産うなぎを届けることができるのです。
まず確認すべきはパッケージの原産国表示です。
「国産」「養殖:日本」という表記があれば国産うなぎですが、
単に「うなぎ蒲焼」とだけ書かれている場合は要注意。
小さな文字で「原材料名」の欄に「うなぎ(中国産)」などと記載されていることがあります。
国産うなぎの特徴はその身の締まりと脂の質にあります。
国産うなぎは筋肉質で引き締まった身質を持ち、噛むと弾力があります。
対して外国産は柔らかすぎることが多く、
うなぎ本来の食感が損なわれがちです。
とはいえ、メーカーによって
品質も力を入れているところはかなりクオリティも上がってきているので
一概に外国産だからといって敬遠する必要はありません。
また、脂の質も異なり、国産うなぎは上質な脂が均一に分布しているため、
口に入れた瞬間にとろけるような食感を楽しめます。
値段も見分ける重要なポイントです。
一般的に国産うなぎは外国産に比べて2〜3倍ほど高価です。
あまりにも安いうなぎは国産でない可能性が高いでしょう。
国産うなぎの美味しさの秘密は、実は養殖技術と餌にあります。
日本の養殖業者は何世代にもわたって培った技術で、
水質管理や餌の配合を徹底しています。
特に餌は魚粉を主体とした高タンパク質のものを使用し、
成長に合わせて調整されています。
これが国産うなぎならではの風味と
旨みを生み出す源となっています。
また、蒲焼の調理法も国産うなぎの美味しさを引き立てます。
日本の伝統的な「江戸前」の調理では、蒸してから焼く
「蒸し」という工程があります。
この手間のかかる工程がうなぎの脂を程よく抜き、
ふっくらとした食感を生み出します。
国産うなぎを見分ける目を持つことは、
絶滅危惧種に指定されている日本のニホンウナギを守ることにもつながります。
適切な価格で流通している国産うなぎを選ぶことで、
持続可能な養殖業を支援することができるのです。
次回、うなぎを買うときは、これらのポイントを思い出して、
本物の国産うなぎの美味しさを堪能してみてください。
その違いは、一口食べれば明らかに感じることができるはずです。
3. うなぎ養殖のカラクリ:
持続可能な未来のために私たちができること

うなぎ養殖は実はとても複雑で大変な産業です。
天然ニホンウナギの稚魚(シラスウナギ)の捕獲から始まり、
育成、出荷まで専門的な知識と経験が必要とされています。
しかし、乱獲や環境変化によりシラスウナギの漁獲量は年々減少し、
国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでは
「絶滅危惧IB類」に指定されるほど深刻な状況です。
養殖現場では、稚魚の高騰が経営を圧迫しています。
静岡県浜名湖のうなぎ養殖業者の間では
「一匹のシラスウナギが数年前の5倍以上の価格になることもある」と語ります。
これは天然資源でもあるシラスウナギが毎年一定量取れる保障がないことから
その希少価値から価格差が生まれてしまいがちです。
とはいえ、
極端に市場価格が急激に値上げされないよう、
裏での努力を地道に行っている背景としては
いったん組合でその値上がり分を負担し、
急激に値段があがらないよう調整弁のような働きをしております。
持続可能なうなぎ養殖への転換点として注目されているのが「完全養殖」です。
宮崎県の水産試験場が先駆的に研究を進め、
近畿大学は世界で初めて人工孵化したウナギの商業出荷に成功しました。
しかし、まだコスト面や安定供給の課題があり、広く普及するには時間がかかります。
消費者としてできることは、「国産うなぎ」の選択だけではありません。
ASC(水産養殖管理協議会)認証を受けた養殖場の製品を選ぶことで、
環境に配慮した生産方法を支援できます。
また、うなぎを食べる頻度を見直し、
特別な日の贅沢品として楽しむという考え方も広がっています。
さらに「代替タンパク質」の可能性も模索されています。
植物由来の原料でうなぎの風味や食感を再現する研究が進んでおり、
大豆やこんにゃくを使った「うなぎもどき」は既に一部飲食店で提供されています。
持続可能なうなぎの未来のためには、
生産者、流通業者、消費者がそれぞれの立場でできることを実践していく必要があります。
うなぎという日本の食文化を守りながら、
次世代に継承していくための新しい形を模索する時期に来ているのです。
4. 「土用の丑の日」だけじゃもったいない!
季節を問わず楽しむうなぎの新提案

うなぎといえば「土用の丑の日」というイメージが強く定着していますが、
実はこの習慣が国産うなぎの需要と供給のバランスを崩す一因となっています。
特定の日に消費が集中することで、養殖業者は短期間に大量出荷する必要があり、
計画的な生産が難しくなっているのです。
国産うなぎの持続可能な消費を考えるなら、
「一年中うなぎを楽しむ文化」への転換が必要です。
秋から冬にかけては脂がのって最も美味しくなる時期。
この季節のうなぎは濃厚な味わいが特徴です。
私の地元では冬季に丑の日の「うなぎ祭り」を開催し、
冬のうなぎの美味しさを発信して新たなうなぎの魅力を地元から親しまれるよう活動しています。
また調理法のバリエーションも豊富です。
伝統的な蒲焼だけでなく、うな茶漬け、うなぎのパスタ、
うなぎのリゾットなど、和洋折衷の創作料理も増えています。
家庭でも手軽に楽しめるよう、蒲焼以外の加工品も充実してきました。
うなぎの白焼きを使ったアヒージョや、うなぎの肝を使ったペーストなど、
スーパーやオンラインショップで購入できるうなぎ製品は多様化しています。
さらに、うなぎの未利用部位を活用した商品開発も進んでいます。
頭や骨を使った出汁パック、皮を使ったコラーゲンスープなど、
うなぎ一尾を余すことなく使い切る取り組みは、持続可能性の観点からも注目されています。
国産うなぎを守るためには、消費者の私たちも「土用の丑の日」以外にも
うなぎを楽しむ習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。
季節ごとの味わいの違いや多様な料理法を知ることで、うなぎ文化の奥深さを再発見できるはずです。
5. プロが教える!
国産うなぎを100%楽しむための調理法と選び方

国産うなぎの魅力を最大限に引き出すには、適切な選び方と調理法が不可欠です。
良質な国産うなぎを見分けるポイントは「艶と弾力」にあります。
まず選び方については、産地表示を確認することが重要です。
国産うなぎには「国産」または「養殖」と表示され、
愛知県三河一色や鹿児島県大隅半島など有名産地のものは特に品質が安定しています。
また、JAUAやASC認証など持続可能な養殖を証明するマークがあるものを選ぶことで、
環境に配慮した消費ができます。
うなぎの調理法といえば蒲焼が代表的ですが、白焼きや串焼き、
うな重以外にも多様な楽しみ方があります。
例えば、うなぎの肝を使った「肝吸い」は栄養価が高く、
独特の風味が楽しめる一品です。
また、うなぎのかば焼きを細かく刻んで混ぜた「ひつまぶし」は、
名古屋発祥の食べ方で三通りの味わいが楽しめます。
うな丼を自宅で美味しく食べるコツとしては、
うなぎを温める際に直火ではなく、蒸し器や電子レンジで程よく温めることが大切です。
また、タレを別添えで購入し、食べる直前にかけると風味が長持ちします。さ
らに、山椒は最後にほんの少量をふりかけるのがプロの技。
多すぎるとうなぎ本来の味わいが損なわれます。
うなぎの栄養を無駄なく摂取するためには、
頭から尻尾まで余すことなく食べることがおすすめです。
特に骨や皮には豊富なカルシウムやコラーゲンが含まれています。
うなぎの骨をカリカリに揚げた「骨せんべい」なども通の間では定番メニューです(^^)
最後に、国産うなぎを楽しむ際は、食べ比べも一興です。
関東風の蒸してから約タイプと
関西風は蒸しを入れずにタレをつける製法で香ばしさが特徴です。
それぞれの調理法の違いを知ることでまた楽しみの幅も広がりますよ!